(お気持ち表明的な文章なので、以下の記述に飛躍や暗黙の前提はたくさんあると思う)
功利主義は最大幸福だけを求める薄っぺらい思想であり、何かと合理主義や資本主義と結び付けられ、人格の別個性を無視する浅はかな思想であり、マイノリティに抑圧的である、などと言われる。功利主義に対して否定的な哲学者、思想家は、このような功利主義に対して対抗的な立場を打ち出す。それは、その思想の構成要素それ自体に、上記にような批判を回避するための要素が組み込まれている。だから自身の理論が功利主義に対する批判を回避できるのは自明である。その分、その思想は分厚く、理論的なコミットメントが多くなる。
私は、功利主義が理論的に薄っぺらいことを認めたいと思う。例えば行為功利主義によれば、ある行為の正しさは、その行為のもたらす帰結に含まれる幸福の総和、そしてそれだけによって決まる。これほど理論的に単純明快な主張はないと思う。この点で功利主義は薄っぺらい。
しかし、批判者等も指摘するように、行為の正しさを知るうえで、その行為のもたらす帰結に含まれる幸福の総和を知らなければならないわけだが、これは非常に困難である。さらに功利主義の実践はときに困難であることもよく批判されている。私はここにこそ功利主義の分厚さがあると思う。このことを以下で示していきたい。
功利主義批判の典型例を見よう。例えば、よく指摘される事例として、臓器移植ケースを見てみよう。このケースでは、5人の人がそれぞれ別々の臓器移植を必要としており、そこに見ず知らずの他人が治療のために運び込まれてくる。いま医者であるあなたがこの人を殺して臓器移植をすれば5人が救われる。しかしこの人を殺さず治療して送り返せば、臓器移植を待っている5人は死んでしまう。この1人を殺しても誰にもバレず、他に悪影響も及ぼされないと仮定しよう。このような仮定によって、この1人を殺して臓器移植するのが最善になるから、功利主義によれば、殺して臓器移植することが道徳的に正しい行為である。しかし、これは直観的に受け入れがたい。
このような事例に対する功利主義からの反論を、ジェームズ・レイチェルズ&スチュアート・レイチェルズは『現実をみつめる道徳哲学』*1において三つにまとめている。
- 功利計算を正しく行えば直観に反する結論は出ない(功利計算の誤り)。
- 修正された功利主義を採用すれば直観に反する結論は出ない(功利主義の修正)。
- 直観は必ずしも信用できない(直観に反する結論の受け入れ)。
私が注目したいのは1や3のタイプの反論である。上の事例の仮定はかなり疑わしい。それはまさに、現実では考えにくい。例えば、第一に、「この1人を殺しても誰にもバレず、他に悪影響も及ぼされない」という仮定は現実ではありえない。第二に、背景にある制度がどのような制度になっているのかは暗黙の了解になっているが、いったいそれはどのような制度設計になっているのか不明である。第三に、この医者や、行為を補助する周辺の人々の気持ちや状況はどうなっているのか不明である。他にも問題点を指摘できるだろう。
功利主義を批判する人々はこのような議論に対して、おそらく以下の三つの反論のいずれかを採用できる。
- 現実的にありえない事例であっても、この事例で功利主義が反直観的な結論を出すのが問題なのだ。他方で自身の理論からはそのような含意はない、というよりむしろ、そのような含意が出ないよう設計されている。だから自身の理論のほうが直観的であり、その点で説得的である。
- そうやって思考実験の不明確な点を埋めなければ帰結を適切に評価できないという点で、功利主義は何が正しい行為なのか評価できないので問題である。他方で自身の理論は、そうした不明確な点を知らずとも結論を出せるので、その点で説得的である。
- 思考実験をより現実に近づけて、それでもなお功利主義からは反直観的な結論が出てくる。他方で自身の理論はそうした現実に近づけた事例であっても反直観的でない事例を出せるために、説得的である。
私は1と2のタイプの道は、その理論が現実に本当に適したものなのか、つまり、現実をみつめているのかを疑う。まず1のタイプの反論から検討しよう。この反論では、現実ではありえない事例で、理論が直観的な結論を出すと主張している。私は、それでいいのか、と言いたい。理由は二つある。第一に、そんな現実でありそうにない事例で適した含意を出せる理論が、現実をみつめた理論になっているとは思えない。第二に、そんなありえない事例ですぐに結論を出せるような理論でいいとは思えない。もっと事例をつぶさに見るような理論でないなら、その理論は、分厚いようでいて、事例のうちで見るべきところを見てないという点で薄っぺらいと思う。
次に2のタイプの反論について、こちらにも同様の指摘が当てはまる。つまり、そんなありえない事例ですぐに結論を出せるような理論でいいとは思えない。事例のうちで見るべきところを見てないから、現実をみつめてないから、そんな短絡的に結論を出せるのだと思う。
以上のように、何か現実的にありえない事例を持ってきて功利主義を批判するとき、実のところそれは功利主義が薄っぺらくないことを示しているのだと私は思う。功利主義は理論的に薄っぺらい。しかしそれを実践に適用した途端に、私達が知らなければならないことが膨大に増える。そのため、正しい行為を知るうえで、功利主義は認識的に過剰要求的である。集めるべき証拠は膨大であり、その証拠に基づいて幸福総和を計算、比較するために要求される推論もまた困難であるからである。
最後の3のタイプの反論は、もしそれが成功するなら、現実をみつめようとする点で良い反論だと思う。そのときにも功利主義が本当に反直観的な結論を出すか疑わしいが、たしかにそういうときもあるだろう。しかしむしろ、時には反直観的な結論を出してほしいと私は思う。
理論が完全に支持者の直観に適合的であるとき、私はそれは、単に保守的なだけの理論に過ぎないと思う。その理論は直観に完全に適合的であるから、理論はその支持者に態度の改善を要求しないだろう。私は道徳理論がこのような保守的なものであってはならないと思う。一部の倫理学者が述べるように、道徳理論は時に、私達の考えを改めさせる修正的役割を持っていなければならないと思う。功利主義はこの点で、他の理論と比較して強く修正的である。私は功利主義を支持するようになってから、幾度となく自分の直観を否定してきたし、修正もしてきた。いまだに反直観的だと思うような実践を功利主義が要求しているとき、できる限りそうしようとしてきた。加えて、最大の幸福を達成することは、自己犠牲を伴うためにしばしば困難である。そのため、功利主義は、実践的に過剰要求的である。自身の直観を否定し、自身の実践を自己犠牲を伴って大幅に変えることが要求されるからである。
功利主義がこのように、認識的にも実践的にも過剰要求的なのは、現実がまさに複雑であるからだと考える。先程の臓器移植ケースに戻ってこのことを考えよう。臓器移植ケースでは、様々なことが暗黙のものにされているが、しかし思考実験の提示者は功利主義批判を目的としているので、功利主義的に1人を殺して臓器移植することが正しくなるよう設計されていると考えるべきだろう。これは、功利主義の過剰要求的な部分を、思考実験の設計によって回避していることを示している。功利主義者がこの事例に対する答えを熟慮する必要がないように思考実験が設計されているため、証拠集めや推論は不要であり、医者であるあなたはこの行為を実践するうえでおそらく心理的負荷もそこまで高くないのだろう(あなたはその行為について黙っていられると想定されるのだから!)。したがってこのような事例では、功利主義がどのように現実をみつめているのかが全く現れてこない。それは思考実験に事前にすべて組み込まれている。
功利主義は、現実の問題について考える限りで、現実をみつめる。正しい行為を知るには、幸福総和に寄与する様々な要因を調べなければならない。そこで自身の素朴な直観は全く信用ならない。自身の行為がもたらす帰結を知るときに、直観が当てになる理由、認識的に信頼できるとする理由が、私には全くわからない。もちろん即座の判断が求められることはあるだろうし、そこで用いることができる方法が直観以外にないときはあるだろう。しかしそうではないなら、例えば効果的利他主義運動が示してくれたように、私達は貪欲に、現実について調べなければならない。幸福に寄与する要因はおそらく、些細なものから重大なものまで膨大にあり、多くのことを知らなければ、私達は正しい行為について知ることができない。私はこれは当たり前のことだと思う。どうして現実の多くを知らずに正しい答えがわかるのか、私には全くわからない。功利主義はこのことを真正面から受け止める。多くのことを知らずして、現実の複雑さを知らずして、正しい行為について知ることはできない。それでも私達がより良い行為を目指すのである限り、私達は現実をみつめ、よく調べ、熟慮しなければならない。功利主義はこのような仕方で現実をみつめている。



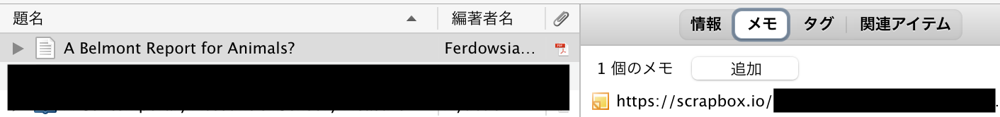
![[改訂第8版]LaTeX2ε美文書作成入門 [改訂第8版]LaTeX2ε美文書作成入門](https://m.media-amazon.com/images/I/41IBo5XilPL._SL500_.jpg)




